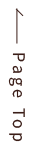- 多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)
- 多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の症状
- 多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の原因
- 多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の診断基準
- 多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の治療方法
- 多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)は痩せると
治るって本当? - 多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)で
気を付けること - 多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)に関する
よくある質問
多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)
 多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)は、卵胞が成熟せず、排卵がうまく行われない状態を指します。通常、月経周期では数十個の卵胞が育ち、1つだけが完全に成熟して排卵されますが、PCOSでは多くの卵胞が途中で成長を止め、小さな未成熟卵胞として卵巣内に留まります。その結果、排卵障害が起こり、不妊の原因となることがあります。
多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)は、卵胞が成熟せず、排卵がうまく行われない状態を指します。通常、月経周期では数十個の卵胞が育ち、1つだけが完全に成熟して排卵されますが、PCOSでは多くの卵胞が途中で成長を止め、小さな未成熟卵胞として卵巣内に留まります。その結果、排卵障害が起こり、不妊の原因となることがあります。
この病気は、20~45歳の女性の5~8%に見られる頻度の高い疾患で、ホルモンバランスの乱れや遺伝的要因が関与していると考えられています。
多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の症状
 多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の症状は個人差がありますが、以下のような特徴的なものがよく見られます。
多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の症状は個人差がありますが、以下のような特徴的なものがよく見られます。月経異常
生理周期が不規則になったり、生理がこない(無月経)といった症状が現れます。
無月経
長期間にわたって月経がこないこともあります。
過少月経または過多月経:月経量が非常に少ないか、逆に非常に多くなることもあります。
排卵障害・無排卵
排卵が不規則または全く行われないことが多く、不妊の原因になることがあります。
男性ホルモンの過剰分泌による症状
多毛症
顔や胸、背中などに毛が生えることがあります。
にきび
顔や背中にできやすくなることがあります。
脱毛(男性型脱毛症)
頭頂部の髪が薄くなる男性型脱毛症が見られることがあります。
肥満および体重増加
PCOSの女性は体重が増えやすく、減量が困難な場合があります。
その他の症状
代謝異常
インスリン抵抗性:血糖値の上昇や高コレステロール血症など、代謝異常が起こりやすい傾向があります。
生活習慣の改善によって症状が軽減する場合もあるため、専門家と相談しながら対応することが重要です。
精神的な症状
うつ病や不安障害などのリスクが高まることがあります。
睡眠障害
睡眠の質が低下し、日中の眠気が増すことがあります。
多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の原因
 多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の明確な原因は解明されていませんが、排卵に関与するホルモンバランスの乱れが大きく関係していると考えられています。
多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の明確な原因は解明されていませんが、排卵に関与するホルモンバランスの乱れが大きく関係していると考えられています。
主な原因
ホルモンバランスの乱れ
卵胞の成長と排卵は、脳の下垂体から分泌される黄体形成ホルモン(LH)と卵胞刺激ホルモン(FSH)によって調節されています。しかし、何らかの要因でLHが過剰に分泌され、FSHに対して優位になると、排卵が障害されることがあります。
アンドロゲン
(男性ホルモン)の影響
PCOSの女性ではアンドロゲンの分泌が増加する傾向があり、これが卵胞の成熟を妨げ、排卵障害を引き起こします。
インスリン抵抗性と
高インスリン血症
肥満や生活習慣の影響でインスリン抵抗性が生じると、体内でインスリンが過剰に分泌されます。この高インスリン血症がアンドロゲンの増加を誘発し、排卵に悪影響を及ぼすことがあります。
これらの要因が組み合わさり、PCOSの発症に寄与していると考えられています
多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の診断基準
日本産科婦人科学会が定める診断基準では、以下の3つの条件をすべて満たし、他のホルモン異常疾患が否定された場合にPCOSと診断されます。
排卵障害がある
排卵が不規則、または無排卵の状態。
高LH血症または高アンドロゲン血症がある
血液検査で黄体形成ホルモン(LH)が高値、または男性ホルモン(アンドロゲン)が過剰に分泌されている。
卵巣に多嚢胞が認められる
超音波検査で卵巣内に多数の未成熟卵胞が確認される。
補足情報
PCOSの症状や程度には個人差があり、上記の診断基準をすべて満たさない場合でも、月経異常や全身症状(多毛やにきびなど)がある場合には、総合的に診断が行われます。
また、PCOSの方では以下の傾向が血液検査で見られることがあります。
- 抗ミューラー管ホルモン(AMH):高値を示すことが多い。
- インスリン値:抵抗性による高値。
診断には、患者様の症状や検査結果を総合的に評価し、適切な治療を選択することが重要です。気になる症状がある場合は、早めにご相談ください。
多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の治療方法
多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の治療は、症状や原因に応じて以下の方法が選択されます。治療の目的は、排卵を促進し、ホルモンバランスを整え、不妊の改善を目指すことです。
排卵誘発剤の投与
排卵を促すために排卵誘発剤を使用します。
ただし、多嚢胞性卵巣症候群では卵巣に多くの卵胞が存在するため、過剰な誘発により次のリスクが生じる場合があります。
多胎妊娠(双子や三つ子など)
卵巣過剰刺激症候群(OHSS):卵巣が腫れたり、腹水が溜まる状態
そのため、排卵誘発剤は必要最小限の量で慎重に使用します。
内服薬(レトロゾール、クロミッドなど)または注射薬が使用され、重症の場合には体外授精や手術を検討します。
肥満の改善
肥満がある場合、適正体重への減量が重要です。
脂肪組織で女性ホルモンの前駆体が作られるため、肥満は卵胞の成長を妨げることがあります。
健康的な減量
無理のない範囲でバランスの良い食事と適度な運動を心がける。
1カ月あたりの減量目標は最大2kg。
インスリン抵抗性改善薬
糖尿病予備軍(耐糖能異常)の場合には、インスリン抵抗性を改善する薬を併用します。
肥満の改善により、正常な排卵が促されることが期待されます。
体外授精
排卵誘発剤や生活改善を行っても妊娠に至らない場合、体外授精を検討します。
メリット
- 多胎妊娠のリスクを低減。
- 高い妊娠成功率。
注意点
- PCOSの患者は採卵時に卵巣出血や卵巣過剰刺激症候群のリスクがあるため、事前に十分な対策を行います。
当院の対応
- 一般的な体外授精(精子を卵子にふりかける方法)
- 顕微授精(精子を直接卵子に注入する方法)
手術
排卵を促進するために手術を行う場合があります。
腹腔鏡下卵巣多孔術(LOD)
- 卵巣に小さな孔を開け、ホルモン状態を改善する手術。
- 多胎妊娠や卵巣過剰刺激症候群のリスクが低い。
多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)は痩せると治るって本当?
適正体重への無理のない減量により、以下の効果が期待されます。
- 自然排卵が起こるようになる。
- 少量の排卵誘発剤で排卵が可能になる。
ただし、短期間の無理なダイエットは逆効果です。
減量目安
- 1カ月で最大2kgのペースで計画的に進めましょう。
多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)で気を付けること
多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の治療や生活管理には、注意すべきポイントがいくつかあります。適切なケアを心掛け、症状の改善や妊娠を目指しましょう。
無理なダイエットはしない
PCOSの方の中には、消化管ホルモンの分泌異常があるため、一般の方よりも食事制限が難しいケースがあります。
極端な食事制限や短期間のダイエットは避け、次のような方法を取り入れましょう。
- 低カロリー食品や栄養バランスの取れた食事を活用する。
- 有酸素運動や筋力トレーニングを組み合わせた運動療法を行う。
無理せず、少しずつ減量することが重要です。
有酸素運動だけに
頼り過ぎない
ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動は効果的ですが、筋力トレーニングを組み合わせるとさらに効果が期待できます。
- 筋力トレーニングは筋肉量を増加させ、基礎代謝をアップさせるため、長期的なダイエット効果が得られます。
- 有酸素運動と筋トレをバランスよく組み合わせることで、健康的な体重管理が可能です。
しっかりと通院すること・治療を継続すること
PCOSは長期的に向き合う必要がある病気です。
- 自己判断で治療を中断せず、定期的に通院し、医師の指示に従いましょう。
- 排卵誘発剤を使用している場合は、卵巣過剰刺激症候群のリスクがあるため、注意深く経過を観察します。
多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)に関するよくある質問
多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)は、放置しても大丈夫?
PCOSを放置すると、以下の問題が発生する可能性があります。
- 月経不順・無月経
- 排卵障害・無排卵による不妊
- 男性ホルモンの過剰分泌に伴う多毛症、にきび、脱毛
- 肥満、代謝異常、精神的問題、睡眠障害
早期に治療を始めることで、これらのリスクを軽減できます。
多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)になると、妊娠がしづらくなる?
はい、PCOSの方は妊娠が難しくなることがあります。多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の方は、そうでない方と比べて妊娠の難易度が高くなる傾向があります。
一部のデータでは、PCOSの方が初めて妊娠・出産する確率は約20%(自然妊娠に限ると約40%)低下し、妊活開始から出産までにかかる期間が平均で2年延びると言われています。
しかし、PCOSだからといって妊娠が不可能なわけではありません。適切な治療を受けることで妊娠の可能性は十分に高まります。妊娠を希望される方は、早期の診断と治療を受けることを強くおすすめします。
多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)になっても、痩せている人はいますか?
はい、痩せている方でもPCOSを発症することがあります。
特に日本人では、肥満がないケースでもPCOSが見られることがあります。他に気になる症状がある場合には、早めに医師に相談しましょう。
多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の薬は保険適用ですか?
はい、一部の治療薬が保険適用になっています。
たとえば、2022年から排卵誘発剤のレトロゾールが保険適用となりました。これにより、治療の選択肢が広がり、費用負担も軽減されています。