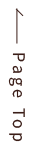不妊治療にはどれくらいの
費用がかかる?
 不妊治療を検討している多くの方が、「費用がどれくらいかかるのか分からず不安」と感じています。
不妊治療を検討している多くの方が、「費用がどれくらいかかるのか分からず不安」と感じています。
不妊症が特定の疾患に起因している場合、その疾患の治療には保険が適用され、患者様の負担は自己負担割合に応じた金額となります。
また、2022年からはタイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精などの高度生殖医療にも保険が適用されるようになり、治療を受けやすい環境が整いました。以下に各治療の費用目安を示します。不明点やご不安なことがありましたら、どうぞお気軽に医師やスタッフへご相談ください。
不妊治療の費用の違い
(タイミング法、人工授精、
体外受精、顕微授精)
※なお、検査内容や使用薬剤によって費用が変わる場合がありますのでご了承ください。
当院では以下の不妊治療に対応しており、患者様のご負担額(3割負担)は以下の通りです。
※検査内容や使用する薬剤によって費用が変わる場合がありますので、予めご了承ください。
タイミング法
基礎体温表、超音波検査などから排卵日を予測し、妊娠しやすいタイミングで性交の機会を持っていただきます。
タイミング法の患者様のご負担額は、1周期あたり数千円~20,000円程度です。
基礎体温表や超音波検査などで排卵日を予測し、妊娠しやすいタイミングで性交の機会を持っていただく方法です。
- 患者様のご負担額:1周期あたり数千円~20,000円程度
体外受精(IVF)
女性から採取した卵子に男性の精子を振りかけて授精させ、その後子宮に戻すことで妊娠を図る方法です。
- 患者様のご負担額:1回あたり12,000円程度
顕微授精(ICSI)
顕微鏡下で女性の採取した卵子に、男性から選別した精子1個を直接注入して授精させ、その後子宮に戻す方法です。
- 患者様のご負担額:1回あたり15,000~40,000円程度
保険適用される不妊治療の
範囲と金額
 2022年より、タイミング法や人工授精といった一般不妊治療に加え、体外受精や顕微授精などの高度生殖補助医療も保険適用の対象となりました。不明点がございましたら、どうぞ医師やスタッフにお気軽にご相談ください。
2022年より、タイミング法や人工授精といった一般不妊治療に加え、体外受精や顕微授精などの高度生殖補助医療も保険適用の対象となりました。不明点がございましたら、どうぞ医師やスタッフにお気軽にご相談ください。
保険適用の対象治療と範囲
以下の治療は中央社会保険医療協議会の審議を経て、関係学会のガイドラインに基づき、保険適用の対象として定められています。
一般不妊治療
- タイミング法
- 人工授精
生殖補助医療
- 体外受精
- 受精卵・胚移植
- 顕微授精
- 胚凍結保存
- 胚移植
これらの生殖補助医療に加え、「オプション治療」として実施される場合は保険適用外となります。ただし、厚生労働省が認めた「先進医療」に該当する治療は、特定の先進医療実施機関で行われます。
例として、PGT(着床前診断)や胚の遺伝子検査が含まれます。
年齢・回数の要件
(体外受精・顕微授精)
保険診療においては、令和3年度までの助成金制度と同様に、以下の条件が設けられています。保険適用の範囲内で適切な治療計画を立てるため、早めのご相談をおすすめします。
| 治療開始時年齢 | 回数制限 (1子ごと) |
|---|---|
| 40歳未満 | 通算6回まで |
| 40歳以上 43歳未満 |
通算3回まで |
窓口での負担額は治療費の
3割負担
不妊治療にかかる費用は、保険適用の範囲内であれば窓口での自己負担額は治療費の3割となります。
また、治療費が高額になった場合には、高額療養費制度を利用することで、月々の自己負担額に上限が設けられます。この上限額や申請方法は、ご加入されている医療保険(国民健康保険または社会保険)の内容によって異なりますので、詳しい情報については、ご加入中の保険制度にお問い合わせいただくか、当院のスタッフまでお気軽にご相談ください。
高額療養費制度を活用することで、経済的な負担を軽減しながら治療を進めることが可能です。
助成金制度で
費用を軽減することは出来る?
 不妊治療に関する助成金制度は、お住まいの自治体によって内容が異なります。対象となる治療や申請条件も自治体ごとに異なるため、詳細についてはお住まいの都道府県や市町村のホームページをご確認ください。
不妊治療に関する助成金制度は、お住まいの自治体によって内容が異なります。対象となる治療や申請条件も自治体ごとに異なるため、詳細についてはお住まいの都道府県や市町村のホームページをご確認ください。
たとえば、神戸市では2022年に体外受精や顕微授精が保険適用となったことを受け、従来の不妊治療助成制度が終了しました。ただし、助成対象となる検査に要した医療保険適用外の医療費の10分の7(不妊治療ペア検査助成事業)については、厚生労働省が認定する医療機関での検査を対象に一部助成を受けられる制度があります(2024年現在)。
最後に
不妊治療に関する費用や助成金制度、その他のご不安な点については、どうぞお気軽に医師やスタッフにご相談ください。当院では、皆様のご希望に寄り添いながら、妊娠を目指して共に歩んでいけるよう全力でサポートいたします。