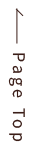不育症の定義とは?
 不育症とは、「妊娠したものの流産や死産を2回以上繰り返す状態」を指します。国内では、不育症に悩む方が数万人いるとされています。
不育症とは、「妊娠したものの流産や死産を2回以上繰り返す状態」を指します。国内では、不育症に悩む方が数万人いるとされています。ただし、不育症であっても、適切な治療によって妊娠の継続や出産が可能になる場合があります。お悩みの方はぜひ当院にご相談ください。
不育症の原因
不育症の原因として、胎児の染色体異常や抗リン脂質抗体症候群がもっとも大きな要因とされています。その他、以下のような要因が流産・死産のリスクを高め、不育症を引き起こすことがあります。
両親や胎児の染色体異常
両親のどちらかの染色体異常 (6%)
両親のどちらかに「均衡型転座」という染色体異常がある場合、流産リスクが高くなります。
均衡型転座とは、ある染色体の一部が別の染色体の一部と入れ替わっている状態で、親には問題が現れませんが、卵子や精子形成時にアンバランスが生じることで流産を引き起こします。
胎児の染色体異常
通常2本である染色体が3本ある「トリソミー」に代表されるように、胎児の染色体数に異常があると、流産リスクが大幅に増加します。
抗リン脂質抗体症候群 (10.7%)
「抗リン脂質抗体」という自己抗体が血液を固まりやすくし、流産や血栓症のリスクを高める病気です。治療には、低容量アスピリン・ヘパリン併用療法が有効とされています。
子宮の先天異常 (3.2%)
「中隔子宮」に代表されるような、子宮の先天的な形態異常が流産のリスクを高める場合があります。手術でリスクを低下させることが可能です。
加齢
高齢出産では胎児の染色体異常リスクが増加し、流産しやすくなります。さらに、男性についても加齢による精子の質の低下が不育症に関与することが知られています。
女性の内分泌疾患
甲状腺機能低下症や糖尿病などの内分泌障害がある場合、流産リスクが高まる傾向があります。
不育症になりやすい人とは?
不育症のリスクは、さまざまな要因によって高まる可能性があります。以下に、不育症になりやすい特徴やリスク要因をご紹介します。
年齢
- 女性:35歳以上の方
- 男性:40歳以上の方
女性の場合、35歳以上になると流産や不育症のリスクが高まることが知られています。加齢に伴い卵子の質が低下し、妊娠の維持が難しくなる可能性があります。
男性の場合も、40歳以上で精子の質が低下し、妊娠に至りにくくなることがあります。
体の状態
- 子宮の形態異常(例:中隔子宮など)
- 甲状腺機能異常(甲状腺の働きに問題がある)
- 血液が固まりやすい体質(例:抗リン脂質抗体症候群など)
甲状腺の異常はホルモンバランスを崩し、妊娠維持を難しくする要因の一つです。また、血液凝固異常による胎盤機能低下も不育症のリスクとなります。
生活習慣
以下の生活習慣が不育症のリスクを高めることがあります。
- 喫煙(本人または周囲の受動喫煙)
- 過度の飲酒
- 過剰なカフェイン摂取(1日200mg以上)
- 体重の過不足(肥満または痩せすぎ)
- ストレスの多い環境
- 運動不足
- 栄養バランスの悪い食生活
ポイント
たばこや過剰な飲酒は血流を悪化させ、妊娠の維持を妨げます。カフェインの過剰摂取も流産のリスクを高める可能性があり、適量を心がけることが推奨されます。
その他
- 過去に流産を経験している
- 家族に不育症や流産を経験した方がいる
遺伝的な要因や既往歴も、不育症のリスクを高める可能性があります。
注意点
これらの特徴があるからといって、必ずしも不育症になるわけではありません。また、これらのリスクがなくても不育症になる可能性があります。ただし、現代の医療では、不育症の治療法は大きく進歩しています。
ご相談をおすすめします
専門的な検査や診断を受けることで、適切な治療を行い、多くの方が妊娠を継続できるようになります。お悩みの方や、過去に流産を経験された方はぜひお気軽にご相談ください。
不育症の治療
不育症の治療は、原因に応じて選択されます。以下は、主な治療法とその内容です。
内分泌異常に対する治療
内分泌異常が原因の場合、ホルモンバランスを整える治療を行います。
- プロゲステロン補充療法
黄体ホルモン(プロゲステロン)が不足している場合、ホルモンを補充することで妊娠維持をサポートします。
- プロラクチン過剰に対する薬物療法
プロラクチンの分泌が過剰な場合、薬を用いて正常値に戻します。
- 甲状腺機能異常に対する治療
甲状腺ホルモンの過不足を薬物療法で調整します。
- 糖尿病に対する治療
食事療法、運動療法、または薬物療法を組み合わせて血糖値を管理します。
抗凝固療法
血液が固まりやすい体質(例:抗リン脂質抗体症候群)が原因の場合、血流を改善する治療を行います。
- 低用量アスピリンの内服
血液をさらさらにして、胎盤への血流を改善します。
- ヘパリン注射
血液凝固を抑えることで、流産リスクを軽減します。
手術
先天的な異常や器質的な問題が原因の場合には、外科的治療が選択されることがあります。
- 子宮形態異常の矯正手術
例:中隔子宮を切除する手術など。
- 子宮筋腫の切除
子宮内にある筋腫を取り除き、妊娠環境を整えます。
- 下垂体腫瘍の摘出
ホルモンバランスを乱す腫瘍を除去します。
不育症はどうやって分かる?
検査方法
流産や死産を繰り返す場合、不育症が疑われます。その原因を特定するために、以下の検査が行われます。
内分泌検査(血液検査)
妊娠継続に必要なホルモンの状態を確認します。
- 甲状腺機能:甲状腺ホルモンが正常かを確認します。
- 下垂体ホルモン:妊娠の調節に関わるホルモンのバランスを評価します。
- プロゲステロン(黄体ホルモン):着床や妊娠維持に必要なホルモンが十分に分泌されているか調べます。
- プロラクチン:母乳の生成や生理周期に関与するホルモンで、過剰分泌がないかを確認します。
子宮形態検査(内視鏡
検査・X線造影検査)
子宮の構造を評価し、異常の有無を調べます。
- 子宮鏡(内視鏡検査):膣から内視鏡を挿入して子宮内を直接観察します。子宮形態異常や筋腫の発見に有効です。
- X線造影検査:子宮に造影剤を注入し、レントゲン撮影を行います。子宮や卵管の形状を詳しく確認できます。
自己抗体検査(血液検査)
自己免疫異常が原因で流産が起こる可能性を調べます。
- 抗リン脂質抗体:血液の固まりやすさに影響する自己抗体の有無を確認します。
凝固系検査(血液検査)
血液の凝固機能を調べ、血栓形成リスクを評価します。
血液が固まりやすい状態や、血液凝固に関連する物質の量を測定します。
染色体検査(血液検査)
ご夫婦それぞれの染色体の状態を調べます。
染色体異常:均衡型転座などの染色体異常があると流産リスクが高くなる場合があります。
※この検査で染色体異常が見つかっても、それ自体を治療する方法は現在の医学ではありませんが、治療方針の検討に役立ちます。
不育症の方が妊娠したら?
何週で安心できる?
不育症の方が妊娠した場合、妊娠を維持できるか心配になるのは自然なことです。一般的に、妊娠 12週を超えると流産のリスクは大きく下がり、多くの方がひとまず安心できると言われています。ただし、個人の健康状態や不育症の原因によって異なるため、引き続き専門的なケアが重要です。
妊娠初期(1〜12週)
妊娠初期は、特に流産のリスクが高い時期とされており、全体の流産の約8割がこの期間に発生します。
12週を過ぎると胎盤がしっかり形成され、胎児の成長が安定し、リスクが低下する傾向があります。ただし、12週を超えた後も医師と密に連携し、引き続き慎重に妊娠を見守ることが大切です。
妊娠初期の過ごし方
妊娠初期は、流産のリスクを軽減するために体を大切に過ごすことが推奨されます。以下のポイントに気を付けて過ごしましょう。
定期的な診察を受けましょう
不育症のリスクを抱える妊婦さんは、 定期的な妊婦健診が必要です。
血液検査や超音波検査を通じて、胎児の成長や母体の健康状態を確認します。
異常や不安を感じた場合は、早めに医師に相談しましょう。
ストレスをためない・
体調管理を徹底しましょう
- 過度なストレスは妊娠の維持に悪影響を及ぼす可能性があります。リラックスできる時間を大切にしましょう。
- 激しい運動や重い物を持つ行為など、 体に負担をかける行動は避けましょう。
- 日常生活で疲れを感じたら、十分に休息を取るよう心掛けましょう。
栄養のある食生活を
心がけましょう
バランスの良い食事を心掛け、特に以下の栄養素を意識して摂取することが重要です。
- 葉酸:胎児の神経管閉鎖障害を防ぐ効果があるため、妊娠初期から積極的に摂取しましょう。
- 鉄分:妊娠中の貧血予防に必要です。
- カルシウム:胎児の骨や歯の発育をサポートします。
不育症の治療を
探されている方へ
 不育症は、繰り返す流産や死産に悩む多くの方々にとって、大きな不安を伴うものです。しかし、医療の進歩により、原因の解明や治療法が多様化し、無事に赤ちゃんを授かる方も増えています。もし「不育症かもしれない」と感じたら、一人で抱え込まず、できるだけ早めにご相談ください。当院では、お一人おひとりの患者様の状態に合わせた治療を提供し、分かりやすい説明と丁寧なサポートを心がけておりますので、どうぞ安心して治療をお受けいただけます。
不育症は、繰り返す流産や死産に悩む多くの方々にとって、大きな不安を伴うものです。しかし、医療の進歩により、原因の解明や治療法が多様化し、無事に赤ちゃんを授かる方も増えています。もし「不育症かもしれない」と感じたら、一人で抱え込まず、できるだけ早めにご相談ください。当院では、お一人おひとりの患者様の状態に合わせた治療を提供し、分かりやすい説明と丁寧なサポートを心がけておりますので、どうぞ安心して治療をお受けいただけます。